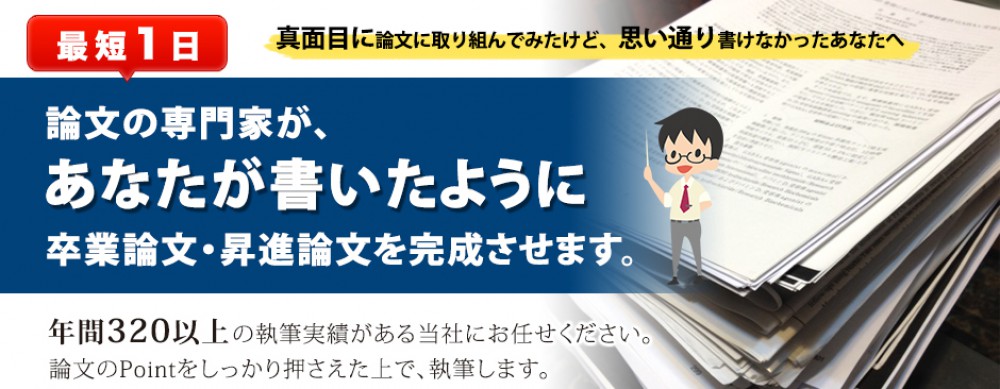こんばんは、顧客サポートの山下です。
最近講習会に参加しておりましたが、そこで即席でプレゼンを行わないといけない事があり、全ての発言に対して断定した言い方をする事には慣れが必要だと実感しました。
「~すると良いと思います」「~が良いかもしれませんね」
これでは言っている事が事実に基づいた事ではなく、自分の考えで話しているように聞こえます。プレゼン時では意識して断定して言い切るようにしていても、特に質問を投げかけられた時に、ついつい「そうですね…○○を実践する事によって結果が出てくると思います」等と返してしまいがちで、多くの人が指摘されていました。
データがきちんとあり、過去の研究から確実に効果が出ていると分かっている事なら、自分の憶測ではないので「断定してください!」と何度も念押しされました。勿論、曖昧だと思う事については「私はその点は把握していないので」ときちんと断りを入れて、勝手に事実を作り上げるのもダメです。
プレゼンや質疑応答とは違い、論文では何度も読み直しをする事ができ、じっくり考えながら書くというメリットがあります。しっかりと論文を読み直し、事実に基づいて論理的に書かれているか確かめる事は大切です。
また、講習会で指摘されたのが言葉の意味の微妙な認識の違いについてです。
私が行った講習会は幼児の言葉の吸収や発達についてのものでしたが、例えば、「赤ちゃんは母親の言っている事を真似をして意味の無い言葉を発します」と言う事は厳密にいうと間違いだと指摘されました。「言葉」には意味があります。「赤ちゃんは母親の言っている事を真似して意味の無い音を発します」というのが正しい。それが「言葉」になった段階で、意味を持ってその音を発している事になる。
細かい事かもしれませんが、講師の方ご自身も研究者で論文を書いており、あやふやな言い方ではなく適切な言葉選びを指導して下さりました。誤った情報を私達が多くの人に流さる事も防いでくれます。「こういう意味で言ってるんだよね」と、伝われば良い、というものではないですね。
話し言葉、特に日本語は雰囲気で伝わるという部分が多い言葉です。Ting-Toomuy, S. (1999) Communicating across cultures. The Guilford Press の論文によると、日本はHCC(High Context Culture)である。言葉一つに沢山の意味を含めて話す文化であるという意味ですが、例えば「また今度集まろうよ」とその気じゃないのに言う事がありますよね?言葉と意味が合っていないのです。外国人がそのような日本人の態度が理解できないと街頭インタビューでつい数日前に答えているのをテレビで見ましたが、HCCの文化を理解するのは逆のLCC(Low Context Culture)の文化圏の人には難しいのです。
しかし、論文、プレゼン、仕事のメール等の場では全てがLCCに変わります。書いてあるそのままその通りの意味に全てを受け止める事が求められます。普段はHCCの中で生活する日本人も、ビジネスになるとLCCを意識しないといけないのですね。
弊社が電話ではなくメールでのやりとりをお願いしている所は言葉のニュアンスを無くす為です。言葉ですと抑揚によって意味が変わる事があります。メールには抑揚は無いので、書いてある意味そのままを読み取ります。「恐らくこういう意味だろう」と曖昧な判断をしては危険ですよね。「いつもなかなか合格がもらえなくて、困っています。」というメールから想像では「このメールを送った人はレポートを書く事が苦手で合格を貰えていないんだな」と想像できますが、「この人がレポートを書く事が上手くて、先生が期待してしまって必要以上の負担を生徒にかけていた」なんて事だってあるかもしれません。書いてある事はそのままの意味として受け止める事が「受け止め方の違い」という事を引き起こしません。
また、電話のやりとりでは、お電話頂いた内容と原稿の内容が食い違っていたとしても証拠はどこにもありません。同じ漢字で音が同じものも沢山あります。似ている音も沢山あります。聞き間違いかもしれません。言い間違いかもしれません。認識の不一致だったかもしれません。これらをメールでお送り頂く事でトラブル防止にも繋がります。
日本語は奥が深いですね!難しい言語ですが、シンプルに使用する事も大切だと感じました。