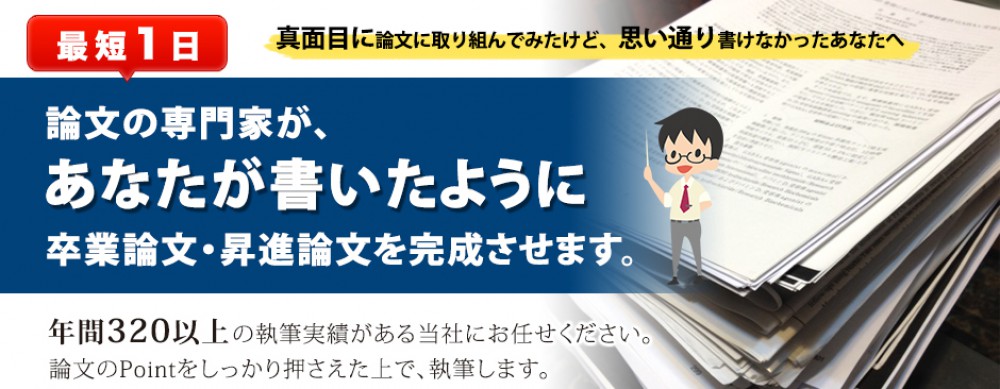こんばんは。夏も蒸し暑い日が続いていますね。
さて、今日は研究発表で緊張せず話す方法についてお伝えします。
まずは、研究発表原稿を依頼された方からのお礼を紹介します。
☆依頼主様からのお礼
多くの方から、ユニークで、興味深い研究発表であると、高い評価をいただきました。
誠にありがとうございました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
☆☆解説
依頼主様のプレゼンスキルも高いものだと予想されますが、発表は多くの方の視線も浴び、非常に緊張の伴うものです。せっかく素晴らしい研究成果が出ていたとしても、プレゼンがうまくいかないと、研究自体も「たいしたことがないのかな?」と思われてしまいます。そこで、簡単なコツを三点お伝えします。
1 最初にどんな話をするのかと、概要を話す
研究した本人には当たり前のことでも、話を初めて聞く人にとっては、わからないことがいっぱいです。なので、極端な話、弟や妹がいらっしゃる方は、彼らに話しかけるイメージを持つといいでしょう。弟や妹がいない場合は、2つ以上下の後輩に話すイメージで。中には、指導教官や専門家の方も話を聞かれる場合もありますが、専門分野や研究テーマが異なる場合、話についていけないケースも散見されます。ですから、初心者の方にでも通じるように、簡単に話すことが大切です。
そのため、最初に簡単にテーマを述べ、聞き手の負担を緩和するためにもポイントが何点あるのかも説明すると良いでしょう。
例えば、
「本日はプレゼンスキルを磨くためのコツをお話ししたいと思います。今日お伝えするポイントは三点あります。一点目は、最初に全体図を示すこと。二点目は、話はゆっくりすること。三点目は、身近な例を挙げることです・・・:
といった感じです。
2 ゆっくり話す
上の事例で出してしまいましたが、緊張して早口になってしまうと、聞き手にも緊張が伝わってしまいます。また、話が早すぎて、聞き手の理解を妨げたり、時間を大量に余らせる恐れもあります。
ところで、発表の際に、どこを見ればいいと思いますか?手前の聞き手?自分の原稿?
「発表用原稿を見ないと話せないよ!」という方もいると思いますが、観客の気持ちとして、自分の方をちっとも見てくれず、ずーっと手元の原稿を見ている方を見たとき、どう思いますか?
というわけで、発表用原稿がある場合でも、定期的に全体を見渡しましょう。部屋全体を見るほど心の余裕もない場合は、一番後ろの席の方に視点を合わせましょう。そうすると、部屋内の大多数の方は、「僕に向かってはなしかけてくれている」という感覚を持ちます。また、あなたが話しているときも遠くの方を見る場合は実は緊張しにくくなります。
3 身近な例を挙げる
これも上の例で挙げていますね。
「日本の食料自給率は低下しているが、食生活水準を考慮するなら、そもそも自給率という指標に疑問を呈すべきだ」
「戦争中の日本の食糧自給率はほぼ100%でした。自給率は高ければ高いほどいいと思われがちですが、戦争中の日本の食事内容は、ごはん、味噌汁、さつまいも・・・どうですか?この食生活体験してみたいですか?」
いずれも、食糧自給率の指標について説明していますが、前半の話で意味はわかりますか?それに対して後半の話だと、小学生高学年が相手でも通じます(筆者が実際にやってみました!)。
話がそれますが、自給率は、「食糧の貿易をまったくしないのであれば、国内に一切外国の食糧がない」ので、必然的に100%になります。
というわけで、難しい話も、どうしたら誰もがイメージできるものになるのだろう?と考えてみるのも大事なことです。
他にもさまざまなコツがありますが、発表用原稿も書ける屋では承っています。
大事なプレゼンや発表の際には、お気軽にご相談いただければと思います!