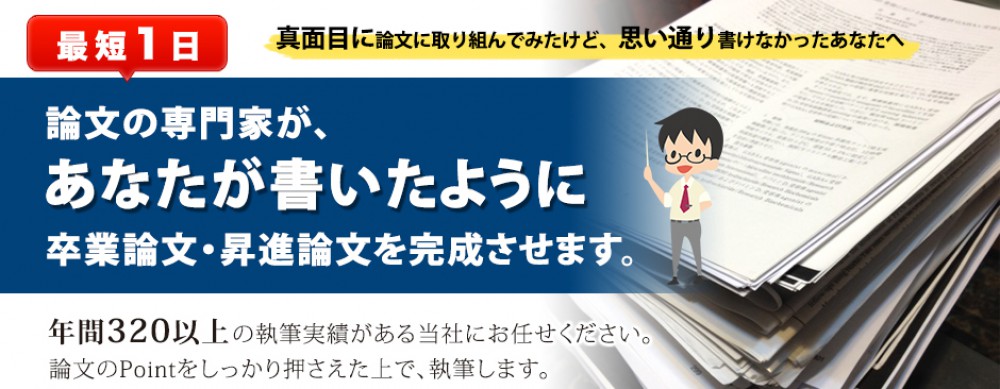おはようございます。今日は昇進論文のお礼を頂いたので、まずは依頼主様のコメントをご紹介します。
☆依頼主様のお礼
早々の訂正ありがとうございます。
こちらの内容で大丈夫です。
ありがとうございました。
☆☆解説
昇進試験論文代行の場合、「社内事情についてどうするのか?」が重要な点の1つになります。書ける屋では、依頼主様から差支えない範囲で情報を聞かせて頂いた上で執筆に取り掛かっております。しかし、「どこまで伝えていいかわからない」「とりあえず差しさわりない部分を伝えたけど、思ってた原稿と違ってた」という場合もあるので、上記のコメントで「早々の訂正ありがとうございます」と頂いているように、依頼主様から指摘事項があれば、速やかな修正を心がけています。
期日ギリギリまで自力で論文を頑張られる方が多いので、残り時間が少ない場合に備えて、書ける屋では執筆者の対応力向上や執筆力向上に取り組んでいます。