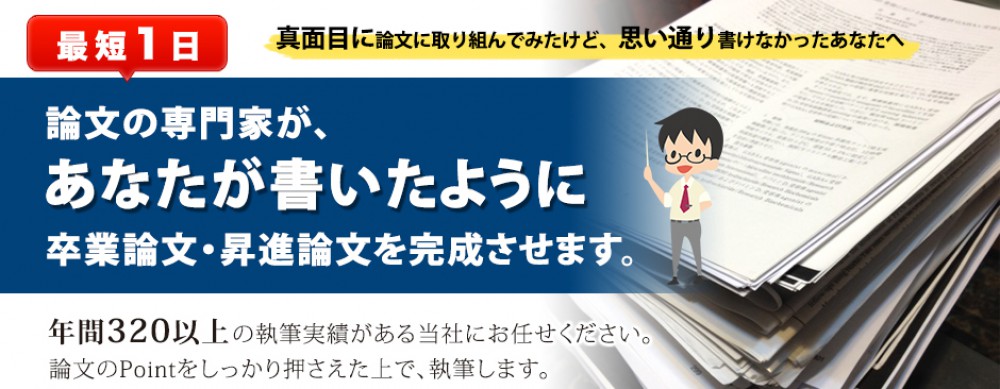卒論のテーマの決め方を前回卒業論文 テーマの決め方でもお話しましたが、その際に章立てについても少し説明しました。
さらに詳しく、章立てについてお話しましょう。
章は「章」→「節」→「項」の順に大きいまとまりから小さいまとまりへと変わります。
例えば地球温暖化を防ぐための私達の課題について書くとします。
一言、地球温暖化と言っても様々な原因がありますよね。
・自動車の排気ガス
・工場の排ガス
・家庭の電力消費
・森林伐採
これで
第一章 地球温暖化の原因
第一節 自動車の排気ガス
第二節 工場の排ガス
第三節 家庭の電力消費
第四節 森林伐採
のように、章と節が出来上がっていきます。
それでは進めていきましょう。
上で挙げた温暖化について今行われている対策について考えてみます。今どんな努力が日本で行われているのかを挙げてみましょう。
・省エネ家電の開発
・リサイクルの強化
・ゴミ排出の削減
先ほどの例ではここまででしたが、次はここから更に細かく見ていきましょう。
・省エネ家電の開発
-ハイブリッド車
-高性能触媒の開発
-ノンフロン冷蔵庫
・リサイクルの強化
-ゴミ分別の細分化
-日本のリサイクル技術
・ゴミ排出の削減
-エコ梱包
-レジ袋の有料化
それでは、これを章立てしていきましょう。
第二章 国内の温暖化対策
第一節 省エネ家電の開発
第一項 ハイブリッド車
第二項 高性能触媒の開発
第三項 ノンフロン冷蔵庫
第二節 リサイクルの強化
第一項 ゴミ分別の細分化
第二項 日本のリサイクル技術
第三節 ゴミ排出の削減
第一項 エコ梱包
第二項レジ袋の有料化
どうですか?
どこに何が書いてあるのかとても分かり易く一目瞭然ですよね。
卒論はページ数が多くなるほどどこに何を書いてあるのかが章立てが綺麗に行われていないとわかりにくくなります。章立てされていないという事は、目次がありません。例えば教科書が章立てされずにもくじが無かったとします。先生が「それでは移植手術における国内の適用可能年齢の引き下げに関する問題につてのページを開いてください」と言ったらどうでしょう。分厚い教科書をぱらぱらとめくりながら敷き詰められた文字だらけのページを必死に探さなければなりません。しかしみなさんの教科書はきちんと目次があるはずですので、本の最初または最後に書いてある「目次」から「心臓移植」と書いてある項目を探して何ページかを調べて開きますよね。
卒論では章立てをすると自分がどういう順番で何を書くのかも分かり易くなり、「これはいらないなぁ」「これは順番を変えよう」「これはもう少し詳しく書こうかな」などと編集も考えやすくなります。卒論の章立てを最初にきちんと考えておく事はスムーズに卒論を書く為に必要な作業です。面倒くさいと思わずに、ぶつけ本番で思い付きのまま書かないできちんと章立てしてから取り掛かりましょう。卒論が書きやすくなり、思いの外すんなり書けてしまうかもしれませんよ。