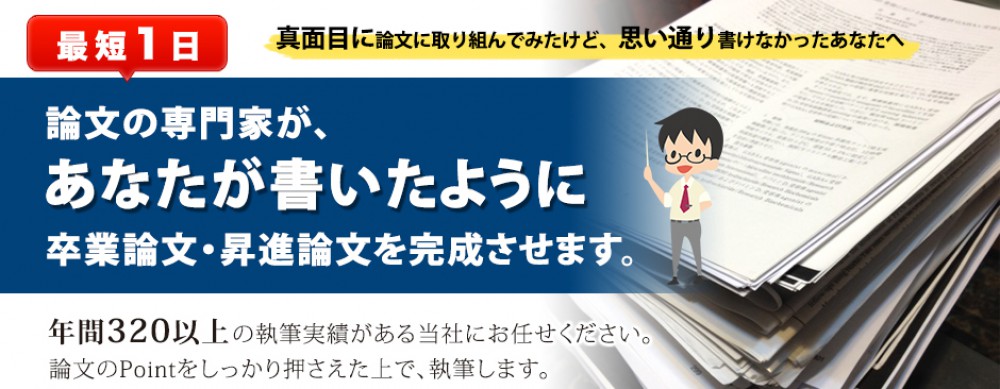サンプル論文の解説をします。サンプルとしてあげた「幼少期のスキンシップ」はこちらへ。
1冒頭部
幼少期の子どもにとって、スキンシップはどのような影響があるのだろうか。また、幼少期におけるスキンシップの量は、子どもが成長していく過程で、本人の成長にどの様に影響していくのだろうか。
まず問題提起ですね。これはレポートでどのような問題文を出されているのかに合わせて変更頂ければ問題ありません。
2具体的な事例を出して論点を絞りに行く
日本では一般的に、触れない(スキンシップをあまりしない)育児方法を行い、情緒的なものを子どもに与えるべきではなく、理性的判断に基づいて接するべきだと言われる。
(中略)
例を挙げると、子どもが何かいいことをしたときの「ご褒美」としてのスキンシップだ。
レポートの質を高めるには、身近な事例やこれまでの見聞を盛り込むことが重要です。また、具体的な経験を冗長に書くのではなく、端的にまとめつつ、「他の場面でも当てはまるよね?」と抽象化すると説得力が増します。
3 背景説明
この背景には、他にも人前でのスキンシップやボディランゲージを恥ずかしいものとみなす考え方もあるからだ。
2で挙げた抽象化です。日本の文化や価値観を盛り込むと、採点者も納得してくれます。
4 調べたことや知っていることを論じる
この定義に当てはめると、日本で一般的に言われている育児方法は、①を大きく制限するため、子どもと母親(もしくは父親)間のコミュニケーション方法が限定されることになる。
(中略)
幼少期からのしつけの一環として「情緒的なものを与えるべきではなく、理性的判断に基づいて接するべき」というのも一理あるし、文化的な根拠もあるのだ。
論文やレポートのコツですが、どちらかの立場に立ちたいとしても、反対意見の根拠も示しておくと、自身の立場を説明する際に、「相手の意見も分かったうえでの反論」が効果的にでき、論文としての価値が高まります。
5 自分の立場を表明して根拠も述べる
こういった背景や意見がある中で、私は、幼少期のスキンシップは育児に対し重要であるから、抱きしめる、さするなどのスキンシップを積極的に行いながら接するべきだと考える。その根拠となる私の考えは2つある(以下略)。
今回のサンプルでは前置きが長く、自分の意見を表明するまでだいぶ時間がかかっていますね(笑)。ですが、しっかりと状況を理解した上での立場表明となっているので、一般的なレポート課題であれば問題ありません。
また、自分の立場を表明するだけでなく「根拠は○点ある」と述べたうえで、それぞれの根拠を述べていくと読みやすくなります。
以上が解説になります。今回のサンプルは他のテーマでも応用がきくので、ひな形としてのご利用はご自由にどうぞ(ただし、そのままコピペすると学校にバレるから、それはやめてくださいね)
関連記事
もっと論文サンプルが読みたいあなたへ(書ける屋論文サンプル)