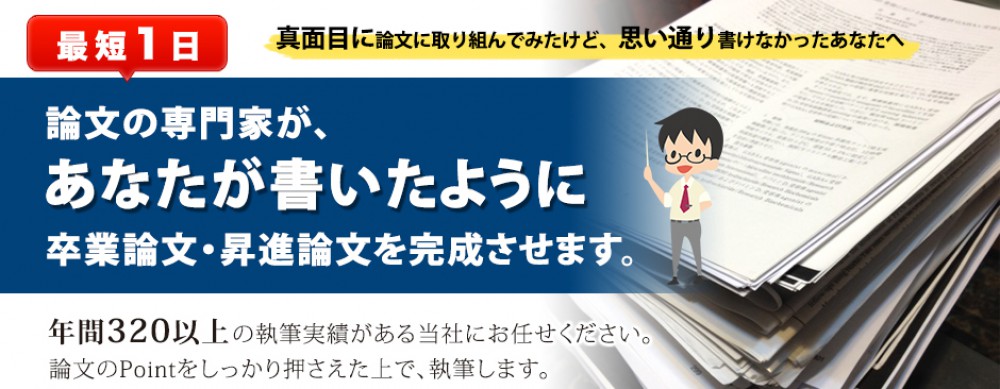連休中に台風が来ることで話題になっていますね。
日本の歴史を振り返ると、台風などの天候は大きな影響を与えてきました。そこで、今日は卒論のテーマとして、天候や気候に着目した考察についてお話します。
「いったいなんだそれは?」と言われる気しかしないのですが、「日本の歴史」「文化「食文化」「庶民の生活」「文学」など、幅広い卒論のテーマで天候や気候に着目した考察は使えるのです!
1 飢饉について
「恵みの雨」という言葉があるように、雨が降らないと米がとれず、その年の日本の食生活は大変なことになります。今の時代であれば、天気予報やアメダスのおかげで、どんな天気になりそうかはなんとなくわかりますし、研究も進められています。でも、昔の日本では古典的な天気予報(雲の形、動物の様子)しかなかったわけですし、雨が降らない理由がなんなのかがわからなかったわけです。
例えば、雨が降らないのは「トップが悪いからだ」「仏様のバチがあたった」といったように、現代では考えられないような理由がまかり通ったわけです。
つまり、当時の天候が不安定だったという記述をみつければ、そこから、文化や宗教に結び付けることが可能になるのです。
2 国内の戦いについて
平安時代末期の平氏と源氏の戦い、戦国時代の合戦など、日本では多くの戦いが繰り広げられてきました。現代の戦争でも天候が与える影響は大きいですが、昔の戦いではもっと影響が大きくなります。身近な例を挙げると、雨の中の山道を歩くのは、地面がぬかるんで大変ですよね?しかも、戦いの際には何百人、何千人もがぬかるんだ道を歩いたり走ったりするので、それこそ前に進んだり後ろに下がったりするのも大変だと予想されます。
ほとんどの戦いは、数が多くて準備万全な方が勝ちます(例外もありますが、桶狭間の戦いのように数が少ないです。なお、桶狭間の戦いも近年ではいろんな研究事例が報告されています)。ですが、この「数の量」を逆転する要素の一つが天気だったわけです。
教科書にも出てくる元寇では、「神風」として台風が決定打を与えたと認識されている方も多いでしょう(ご存知の方もいますが、近年の研究では、天候以前に日本側が相手の上陸を防ぐための工夫や成果が多く報告されています)。
このように、天気に着目するだけで、論文には新たな視点が盛り込まれます。
以上です。行き詰った方はぜひ試してみてくださいね。